第1章:Webマーケティング職とは?業務内容と求められるスキル
「Webマーケティング職」と一口に言っても、その業務範囲は非常に広く、企業によっても担当範囲が異なります。まずは、Webマーケターとは何をする職種なのか、どんなスキルが求められるのかを明確にしておくことが、転職活動の第一歩になります。
■ Webマーケティングの主な業務領域
Webマーケティングの仕事は、大きく分けると以下のような領域に分類されます。
- SEO(検索エンジン最適化)
Googleなどの検索エンジンで上位に表示されるよう、自社サイトやコンテンツを最適化する仕事。キーワード選定、記事構成、内部リンク設計などを行います。 - 広告運用(リスティング・SNS広告など)
Google広告、Instagram広告などを用いて商品・サービスの認知や購入を促進。出稿設計から効果測定、改善施策までを一貫して担います。 - SNSマーケティング
X(旧Twitter)、Instagram、TikTokなどのSNSを活用し、ブランドのファンを増やしたり、商品の話題性を高めたりする役割。投稿企画・運用・数値分析などが中心。 - コンテンツマーケティング
ブログ、YouTube、メルマガなどを通じて価値ある情報を発信し、ユーザーとの関係構築や集客を目指す手法。 - Webサイト分析(Google Analyticsなど)
サイトの訪問数・離脱率・CV率などのデータを分析し、改善点を発見して施策に活かします。
未経験者が最初に挑戦しやすいのは、SNS運用・広告アシスタント・コンテンツ記事作成などの「実行型業務」が多いポジションです。いきなり戦略設計や広告予算管理などの上流業務を担うのはハードルが高いため、ステップを踏む意識が大切です。
■ 未経験でも狙える職種タイプ
「Webマーケター」と言っても、ポジションは複数あります。未経験でも挑戦しやすいのは、以下のような職種です。
- Webマーケティングアシスタント
→ 広告運用やSNS運用を補助するポジション。進行管理やレポート作成などの業務が多く、実務経験を積みやすい。 - オウンドメディア編集/ライター
→ コンテンツ制作に携わりながら、SEOや構成設計を学べる環境。ライティング経験が活かせる。 - 広報・SNS担当(兼任含む)
→ 自社のSNSを活用した情報発信を担当。マーケティング知識は後追いでもOKな場合が多い。 - Web広告の運用補助
→ Google広告やFacebook広告などの入稿・レポート作成業務からスタートするケースも。
これらのポジションで実務経験を積み、ゆくゆくは広告運用や企画立案などの「コア業務」にキャリアアップするイメージが現実的です。
■ 求められるスキルと適性
未経験からWebマーケターを目指す場合、専門スキル以上に「素養」と「伸びしろ」が重視されます。以下のような要素が強みになります。
- 数字への耐性・関心:クリック率、CV率、広告費などの数値を扱うため、数字に抵抗がないこと
- PDCAを回す力:仮説→実行→分析→改善を繰り返す習慣がある人は向いています
- トレンド感度:SNSやWebの変化に敏感で、自ら情報を取りにいけること
- 文章力/構成力:特にコンテンツやSNS運用系では、分かりやすく伝える力が重視されます
- ツール学習への意欲:Google広告、GA4、Canvaなど新しいツールを抵抗なく学べるかどうか
もちろん、これらはすべて完璧である必要はありません。「伸びる予感」を企業に感じてもらえるかが、採用の分かれ目です。
■ 最初に整理しておきたい「向いている/向いていない」の判断軸
最後に、自己分析のヒントとして、「Webマーケに向いている人/向いていない人」の傾向をまとめます。
| 向いている人 | 向いていない人 |
|---|---|
| トライアンドエラーが苦ではない | 正解を求めすぎるタイプ |
| データを見るのが好き | 感覚で判断する傾向が強い |
| SNSやWebに興味がある | PC作業が苦手、苦痛に感じる |
| 変化に柔軟に対応できる | 手順やマニュアルを重視したい |
Webマーケティングは、変化と改善の繰り返しの世界です。飽き性でも全然構いません。「仮説→実行→失敗→改善」が楽しいと思える方にとっては、非常にやりがいのある職種といえるでしょう。
第2章:未経験でも採用される人の特徴とは?企業が見る“伸びしろ”ポイント
Webマーケティング職への転職を目指す際、多くの未経験者が不安に思うのが「実務経験がないと受からないのでは?」という点です。たしかに経験者が優遇されやすいのは事実ですが、未経験でも採用されている人は多数存在します。そのカギとなるのが、企業が重視する「ポテンシャル=伸びしろ」です。
この章では、企業が“伸びしろを感じる人材”に共通する特徴を解説します。
■ 企業が見る「伸びしろ」とは何か?
伸びしろとは、単に「やる気がある人」ではありません。以下のような要素があるかどうかで、企業は将来的な成長可能性を判断します。
- 吸収力:知識・スキルを素早く取り入れる力
- 主体性:自分から学び、動く習慣があるか
- 論理的思考力:数値や因果関係を整理して話せるか
- 発信力/表現力:伝え方が明快であるか
Webマーケティング職では、インプットとアウトプットの速度と質が業務成果に直結するため、「一緒に働いたら成長してくれそう」と感じさせるかが非常に重要です。
■ 「伸びしろを評価されやすい」参考例
✅ ケース1:前職が営業職の20代女性
- 面接で「SNSの投稿を毎日続け、フォロワーを1000人にした」経験を紹介
- 数値を交えて成果と工夫を説明
- 自発的にPDCAを回していた点を評価され、広告代理店のアシスタントに内定
→ 実務でなくても、数字を伴った成果があると説得力が増す
✅ ケース2:飲食業界から転職を目指した第二新卒
- 独学でGA4を触って簡易レポートを作成し、ポートフォリオとして提出
- 分析に対する興味や理解の深さが評価され、自社メディア運営会社に採用
→ 「学んでみた」「使ってみた」の行動が意欲の裏付けになる
■ ポテンシャルを伝える具体的な工夫
未経験者でも、工夫次第で「伸びしろ」を面接で伝えることは可能です。以下のようなポイントを押さえましょう。
① 実績の“種”を持っておく
完全な実務経験でなくても、「ブログ運営」「SNSの投稿」「広告アカウント開設」など、触れてみたことがあるだけでアドバンテージになります。例えば:
- noteやWordPressで記事を5本書いた
- Instagramで企業アカウント運用のシミュレーションをした
- Google広告の模擬プランをスプレッドシートにまとめた
このような「スモールチャレンジ」をポートフォリオにしておくと、信ぴょう性と意欲の両方を伝えられます。
② 言語化と論理構成を磨く
Webマーケターは「なぜそうしたか」を言語化できることが非常に重視されます。たとえば面接で次のように伝えられると好印象です:
「Instagramの投稿では、ユーザーの閲覧時間が長い『リール動画』に注目しました。競合分析から“BGMと字幕の工夫”が重要だと仮説を立て、実際に視聴維持率が前月比20%改善しました」
→ このような論理構成ができると、未経験でも即戦力に近い印象を与えられます。
■ 採用担当が見ている“質問の仕方”
実は面接で「いい質問ができるか」も見られています。
たとえば以下のような質問ができると、業界への理解度と学ぶ姿勢が伝わります。
- 「広告予算が少ない案件では、どういった施策が有効ですか?」
- 「CTRが上がってもCVが伸びない場合、どこを最初に改善しますか?」
- 「インターンや副業などで学べる環境はありますか?」
逆に、「未経験でも本当に大丈夫ですか?」といった曖昧で受け身な質問は、ネガティブに受け取られる場合があるため要注意です。
■ まとめ:未経験者の武器は“学習と挑戦の習慣”
結論として、未経験でWebマーケ職に転職するには「学びながら動いている人」であることが重要です。
知識やスキルの未熟さは、行動と表現力でカバーできます。
完璧である必要はありません。重要なのは「伸びそうだな」「一緒に働いて成長してくれそう」と思ってもらえるか。そのための準備と表現を、少しずつ積み重ねていきましょう。
第3章:よくある失敗例とNG行動|自己流でやってもうまくいかない理由
未経験からWebマーケティング職に転職するには、準備と戦略が欠かせません。しかし実際には、間違った方向に努力してしまうケースが後を絶ちません。「勉強しているのに受からない」「書類すら通らない」──そうした悩みの裏には、共通する“NG行動”が潜んでいます。
この章では、未経験者が陥りがちなよくある失敗と、その理由を解説します。
■ NG行動①:「資格を取れば安心」と思い込む
マーケティング検定やGoogle広告の認定資格など、学習の一環として取得するのは良いことです。しかし、それだけでは転職に直結しないことも多いです。なぜなら企業は「資格」よりも「使えるスキル」や「実行力」を求めているからです。
資格は“学んだ証拠”にはなりますが、実務では「仮説立て」「数値改善」「クリエイティブ提案」など、実際に動かせるスキルが重視されます。資格だけで安心せず、「何ができるようになったか」をセットで示せるようにしましょう。
■ NG行動②:なんとなく「SNSが好きだから」と目指す
「Instagramが好き」「YouTubeをよく見る」といった動機でWebマーケを目指す人もいますが、それだけでは説得力が足りません。企業側は「なぜWebマーケに興味を持ち、どんな貢献ができそうか」を聞きたいのです。
SNSが好きでも、「どんなアカウントが伸びているか?」「どうすればエンゲージメントが上がるか?」といった視点で見ていなければ、マーケ視点としては浅く映ってしまいます。趣味の延長ではなく、「マーケ的に観察していた」エピソードがあれば、強いアピールになります。
■ NG行動③:自己流でブログを始めて燃え尽きる
「ブログを書き始めました」と話す未経験者は多いです。しかし、独学かつ“戦略なき運営”では成果も出にくく、続けるうちにモチベーションが下がり挫折することがよくあります。
Webマーケティングは「目的→戦略→施策→検証→改善」という流れが重要です。単に「思ったことを綴るブログ」ではマーケ実務の再現性が伝わりません。ターゲット設定やキーワード選定、流入分析といった視点を持たずに走り出すと、やがて「意味がない」と感じてしまいがちです。
■ NG行動④:職種・分野を絞らず、全部応募する
Webマーケティングと一口に言っても、広告運用、SEO、SNS運用、CRM、データ分析など多岐にわたります。それぞれ求められるスキルや適性が違うため、「なんでもいいからマーケティング職に就きたい」と応募を広げすぎると、軸がぶれて選考対策も浅くなります。
企業側も「この人はどこを目指しているのか」が曖昧だと判断しにくくなり、書類通過率が下がることに繋がります。特に未経験者の場合は、「この分野に興味があり、こういうスキルを伸ばしたい」と明確に伝えることで、採用の確度が高まります。
■ NG行動⑤:自己分析を怠り、“なんとなくの志望動機”で挑む
マーケティング職は論理的に物事を考える力が求められる職種です。そのため、面接では「なぜその職種なのか?」「なぜその企業なのか?」をしっかり問われます。
ここで自己分析が甘いと、志望動機が薄く「とりあえずマーケが流行っているから」「リモートで働きたいから」といった理由になってしまい、評価が低くなります。
「前職の●●という業務が、データ分析やユーザー理解につながると感じた」など、自分の経験とマーケティングの接点を具体的に語れると、説得力が一気に増します。
■ まとめ:未経験者こそ「準備不足=不利」になりやすい
未経験からの転職は「準備の質」が明暗を分けます。自己流・無戦略・なんとなくの志望動機は、企業から見て“伸びしろが読みづらい”人材に映ってしまいます。
以下のような行動は避け、戦略的に動くことが成功の第一歩です:
- 資格取得だけに頼らない
- SNSが好きというだけで終わらせない
- 運用や改善視点を持つ
- 軸を持って職種を絞る
- 志望動機を具体化する
第4章:実務経験ゼロからの転職に成功するパターン3選
未経験からWebマーケティング職に内定をもらうには、「知識」だけでなく「実行力」と「論理性」が問われます。実際に成功した方々の共通点を分析すると、次の3つのパターンが浮かび上がってきます。
成功パターン1:学習・実績の精度を高めた
独学で学んだ内容をそのままアピールするのではなく、「学び→実行→振り返り→改善→成果」というPDCAサイクルを意識していた人が内定を勝ち取っています。
- 例:ブログを3ヶ月運営 → アクセス数低迷 → SEO分析 → 改善施策実行 → 流入改善
- 例:SNSアカウントで投稿方針を仮説立て → A/Bテスト → インプレッション2倍
このように、「目的」と「改善努力」がセットになっていると、学びが成果に結びついていることが伝わります。
成功パターン2:履歴書・面接を“マーケ視点”で設計
採用プロセスそのものを「マーケティング」と捉え、相手(企業)の課題を読み解いて「自分をどう活かせるか」という切り口で応募書類を作成・面接対策していた人が多くいます。
- 例:企業の商材や広告を研究し、「LPに誘導する導線設計に興味があります」と明言
- 例:「データ分析×仮説検証」に関心を持ち、前職の数値業務を応用したエピソードを用意
「自分目線」のアピールではなく、「企業にどう貢献できるか」という“打ち手”ベースの対話ができる人は、面接官の印象にも強く残ります。
成功パターン3:選考の土俵に“先に”立った
実務経験ゼロでも、選考の前からインターン・副業・アルバイトなどで“入口の経験”を得ていた人の成功率は非常に高いです。
- 例:マーケ代行会社で3ヶ月だけアルバイト → LP改善やレポート作成を経験
- 例:クラウドワークスで記事執筆 → Googleドキュメントで構成力をアピール
「未経験ですが、○○を3ヶ月やっていました」という実績があると、採用側の安心感は桁違いです。
第5章:ポートフォリオと自己PRの作り方|“実務っぽさ”を演出する
未経験でも、自己PRに「実務っぽさ」を持たせることで、印象を一気に高めることができます。ここでは、採用担当者に響くポートフォリオと自己PRのポイントを紹介します。
ポートフォリオは「実行」+「振り返り」が命
単なる制作物の羅列ではなく、以下のように構成すると、評価されやすくなります。
ポートフォリオ例:ブログ運用の場合
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| 目的 | SEOで特定のキーワードで上位表示を目指す |
| 施策 | キーワード設計/競合分析/内部リンク改善 |
| 結果 | 月間アクセス 300 → 1200に改善(3ヶ月) |
| 分析 | どの施策が効果的だったか、反省点は何か |
このように、「狙い」と「振り返り」があるだけで、“考えて動ける人”として評価されます。
自己PRは「過去の経験×マーケ力」で構成する
たとえ実務未経験でも、過去の仕事の中に“マーケ視点”を見出せることは多いです。
- 店舗スタッフ → 接客データを分析し、販促施策を提案した経験
- 営業職 → 顧客の課題をヒアリングし、資料を改善した経験
これらを以下の構成でPRすると効果的です。
自己PR構成テンプレ
- 経験した仕事と業務内容(簡潔に)
- その中で気づいた課題(仮説立て)
- 自分で試した打ち手(施策)
- それによって得られた成果(定量的に)
この4ステップを押さえるだけで、「未経験でもマーケに通じる行動ができている」と判断されやすくなります。
第6章:Webマーケティング職に強いエージェントの選び方と併用術
Webマーケティング職への転職成功の鍵は「エージェント選び」にもあります。特に未経験者は、サポート内容や求人の質に大きな差が出るため、慎重に選びましょう。
強いエージェントの特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業界特化 | Web・広告・ベンチャーに強い会社を選ぶ |
| 若手支援に実績 | 第二新卒・未経験支援の実績がある |
| 書類添削・面接対策が丁寧 | 決まり切ったテンプレではなく、職種別の対策をしてくれる |
| 自社メディアを持つ | ノウハウ記事やYouTubeなどで信頼性がある |
併用する際の注意点
エージェントは1社ではなく、2〜3社併用するのが理想です。ただし「同じ求人に複数の窓口から応募してしまう」とトラブルになる可能性があるため、以下のルールを守りましょう。
📌 併用のコツ:
- 同じ求人がかぶったら、1社に絞って応募する(どこから応募したか記録しておく)
- 各エージェントに「他社も併用している」と伝える(透明性を持たせる)
- 書類添削や求人提案の精度を比べて、自分に合ったところを残す
複数使いはトラブルではなく「戦略」です。情報収集力と自己判断力を持って動けば、理想の転職が近づきます。
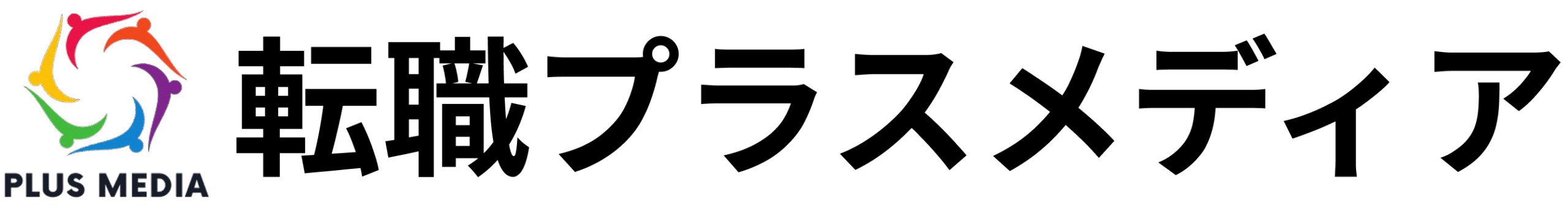

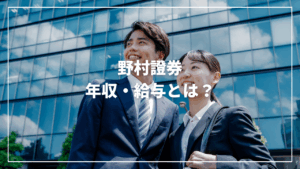
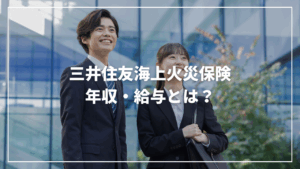






コメント